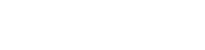- 腸の薬の成分が多すぎて難しい。
- 止瀉と瀉下の性質が、よくわからない。
- 木クレオソートは、なぜ木(もく)なのか知りたい。
この記事では、登録販売者試験に出てくる腸に関する薬をわかりやすく説明しています。
私は、現在ドラッグストアで登録販売者として働いていますが、腸の薬の成分は勉強していて苦戦した成分の1つです。
補足内容が多いので、あなたの持っているテキストと一緒にこの記事を読むと、理解が深まります。
項目が多いので、目次から見たいページをご覧ください。
また、実際の現場で役に立つ豆知識も教えますね。
合格後にもう1回見直したり、活用してみてください。
はじめに:腸の薬のはたらきについて
小腸と大腸は、それぞれはたらきが違ってきます。
- 小腸……大半の水分の吸収
- 大腸……適切な水分量の調整
そして腸のはたらきは、自律神経によって制御されてるんですね。
自律神経は無意識にはたらく神経ですが、
腸以外の病気などで自律神経系を通じて、腸の動きに異常をきたす場合があります。
それが、下痢と便秘です。
- 急性の下痢
…体の冷え、消化不良、食中毒、緊張などのストレス - 慢性の下痢
…腸自体に病気などがある可能性
急性は、昨日までは何ともなかったのに、今日いきなり下痢になる場合です。
慢性は、何日も何週間も下痢が続いている状態です。
このちがいが試験に出るときがあります。
- 一過性の便秘
…環境変化などのストレス、薬の副作用 - 慢性の便秘
…腸の働きの低下、腸管の感受性の低下
一過性は、毎回ではなく一時的なもので、日が経つと改善されるケースです。
慢性は、日頃から便秘気味で習慣的になっている状態です。
通常は直腸に便が溜まると排便反射がおこり、無意識に外に出そうとします。
うんちがしたいという、人間や動物なら必ず起こる生理的欲求ですね。
便意があっても我慢を繰り返し続けると、この反射反応が低下し、便秘の原因になります。
これを腸管の感受性の低下といいます。
腸の薬の種類について
腸の薬は、大きくわけて3種類あります。
- 整腸薬(せいちょうやく)
- 止瀉薬(ししゃやく)
- 瀉下薬(しゃげやく)
整腸薬
整腸薬は、腸の調子やお通じを整えます。
膨満感といったお腹の張り、軟便、便秘改善を目的としている薬で、整腸成分を中心に配合されています。
止瀉薬
止瀉薬(ししゃやく)と読み、止瀉成分をメインの成分として配合されています。
一般的に下痢止め薬と呼ばれる薬で、下痢、軟便、食あたり、水あたりなどの改善を目的としています。
- 食あたり
食中毒のこと。
傷んだものを食べたことで引き起こす下痢 - 水あたり
水分摂取によるもの。
放置して傷んだ飲み物や水道水、硬水を飲んで引き起こす下痢
止瀉薬を飲みすぎると、本来出すべきうんこがなかなか出なくなり、便秘になる場合があります。
瀉下薬
瀉下薬(しゃげやく)と読み、いわゆる下剤です。
主要成分はそのまま、瀉下成分といいます。
瀉下薬は、便秘、便秘にともなう肌荒れ・にきび・食欲不振などの改善を目的としている薬です。
瀉下薬を飲みすぎると、お腹が下りすぎて、下痢を起こす場合があります。
腸の薬の成分について
胃の薬の成分は、たくさんの種類から構成されています。
- 整腸成分
- 止瀉成分
- 収斂成分
- 腸内殺菌成分
- 吸着成分
- 瀉下成分
整腸成分
整腸成分は、腸内細菌のバランスを整えます。
整腸成分は、ビフィズス菌・乳酸菌のような生菌成分と、トリメブチンマレイン酸塩の2つにわけられます。
生菌成分
整腸成分の中でも、生菌成分(せいきんせいぶん)と呼ばれる成分です。
名前のとおり生きた菌で、あなたのお腹に良い効果をもたらしてくれます。
いわゆるヨーグルト・ヤクルトなどに入っている良い菌。
登録販売者試験で出てくるのは5種類です。
- ビフィズス菌
- アシドフィルス菌
- ラクトミン
- 乳酸菌
- 酪酸菌(らくさんきん)
市販薬だと、新ビオフェルミンS錠が有名ですね。
主に、ビフィズス菌やアシドフィルス菌が配合されています。
生薬にも、同じ整腸作用を持つものがあります。
- ケツメイシ(決明子)
…マメ科のエビスグサの種子 - ゲンノショウコ(現の証拠)
…フクロソウ科のゲンノショウコ - アセンヤク(阿仙薬)
…アカネ科のガンビールの葉
ちなみに、ケツメイシという音楽グループがいるんですが、、
グループ名の由来は、整腸成分の「ケツメイシ」が由来だったりします。
※wikipedia(ケツメイシ)参照
ちなみに生菌成分は医薬品成分に該当しないので、生菌成分のみ配合されている新ビオフェルミンS錠は、指定医薬部外品となります。
生薬が配合されているものは医薬品の区分になるので、ザ・ガードは第3類医薬品です。
ザ・ガードは、ビフィズス菌やラクトミンの他に、センブリ、ケイヒ、ウイキョウ(いずれも生薬)が配合されています。
トリメブチンマレイン酸塩
トリメブチンマレイン酸塩は整腸成分にカテゴリされ、「トリメブチン」と省略して覚えてOKです。
トリメブチンマレイン酸塩は、胃腸の平滑筋に直接作用します。
運動が低下しているときは亢進的に、運動が亢進しているときは抑制的にはたらきます。
難しい言い回しですが、
プラスのときはマイナスに、マイナスのときはプラスにはたらいてくれることによって、プラマイゼロにしてくれます。
(悪い状態 → いつもの状態にしてくれる)
亢進的は高ぶらせること、抑制的はおさえることなので、結果的に消化管の調子を整えてくれるということです。
そして、トリメブチンは肝機能、肝臓病に注意です。
(第5章の「次の診断を受けた人は相談すること」の項目にありませんが、覚えておきましょう)
止瀉成分
止瀉成分は、下痢をおさえる成分で、その中でもカテゴリが分かれています。
- ロペラミド塩酸塩
- 収斂成分
- 腸内殺菌成分
- 吸着成分
「ロペラミド塩酸塩」「は他の止瀉成分と作用が異なるので、単体で解説してます。
ロペラミド塩酸塩
「ロペラミド塩酸塩」は腸のぜん動運動をおさえる成分で、腸の無駄な動きをおさえてくれます。
「ロペラミド」と省略して覚えてOKです。
2〜3日使用しても下痢の症状が改善しなければ、受診勧奨の目安になります。
症状によって飲める飲めないの条件があります。
- 向いている〇
…食べすぎ、飲みすぎ、寝冷え - 向いていない×
…食あたり、水あたり
食あたり、水あたりなどの細菌が原因の下痢、インフルエンザなどのウイルスによる下痢には使用できません。
基本的に、細菌・ウイルスを体外に出し切ってしまう必要があるからです。
また、海外で麻痺性イレウスを起こした報告があるため、小児(15歳未満)には使用できません。
登録販売者試験では、麻痺性イレウスはロペラミドの項目しか出てこないので、
「イレウス=ロペラミド」とセットで覚えると良いです。
そして脳や脊髄などの中枢神経系を抑制する作用もあります。
眠気やめまいが起こるため、車の運転などはしてはいけないよう注意が必要です。
これだけ注意点が多い成分なだけに、下痢止め薬としてはトップクラスの効き目です。
それだけに、効き目が強すぎて便秘になる場合があるため注意です。
市販薬だとトメダインという止瀉薬があり、成分がロペラミドのみです。
添付文書に注意点がわかりやすく記載されているので、一度読んでみることをおすすめします。
収斂成分
収斂成分(しゅうれんせいぶん)と読み、収斂は「引きしめる」という意味です。
腸粘膜のタンパク質と収斂成分が結合して、保護膜を作り、腸を引き締めてくれます。
腸粘膜の表面の炎症をおさえ、腸のぜん動運動もおさえ、下痢をおさえます。
収歛成分はこんな感じです。
- 次没食子酸ビスマス
- 次硝酸ビスマス
- タンニン酸アルブミン
- ゴバイシ
- オウバク
- オウレン
収斂成分の注意点は、細菌性の下痢に使用しないことです。
細菌性の下痢や食中毒は「薬で細菌を治す」というより「早く体外に出すこと」が早く治る方法だったりします。
ビスマス系は、収斂作用+有毒物質を分解する作用があります。
次没食子酸(じぼっしょく)ビスマス、次硝酸(じしょうさん)ビスマスは、それぞれ省略して「ビスマス」だけ覚えればOKです。
そんなビスマス、注意点があります。
- 胃、十二指腸潰瘍の診断を受けた人は相談
- 1週間以上の使用禁止
- 服用時の飲酒禁止
- 妊婦は使用禁止
ビスマスは、連用すると精神神経症状が出る可能性があるためです。
また、タンニン酸アルブミンにも注意点があります。
- 重篤な副作用…ショック(アナフィラキシー)
- 使用禁止…牛乳アレルギー
ひっかけ問題として「タンニン酸ベルべリンは牛乳アレルギーの人に使用してはいけない」と出てくる場合があります。
この問題だと、×間違いです。
ベルベリンではなく「アルブミンが牛乳アレルギー不可」です。
※タンニン酸ベルベリンは、腸内殺菌成分で紹介します
また、ロペラミドもそうですが
急性の激しい下痢や吐き気の症状には、市販薬を使う前に医師の診断を優先してくださいね。
別の病気が見つかる場合があるからです。
腸内殺菌成分
腸内殺菌成分は、細菌感染による下痢の症状をおさえます。
前項で紹介したロペラミド・収斂成分は、細菌性の下痢は使用不可なので、ちょうど対になっているんですね。
腸内細菌成分は、以下のとおりです。
- ベルベリン
- タンニン酸ベルベリン
- アクリノール
- 木クレオソート
- オウバク
- オウレン
腸内殺菌成分の注意点として
生菌成分と併用すると、腸内殺菌成分によって生菌成分のはたらきが弱くなってしまいます。
生きた菌を腸に届けたいのに、殺菌したら意味ないですよね、、
ベルベリンは、腸内殺菌作用+抗炎症作用のダブル効果です。
※生薬のオウバク(黄柏)は、ベルベリンを含みます
タンニン酸ベルベリンは、タンニン酸とベルベリンの化合物です。
消化管内で成分が分離して、それぞれ個々の成分が作用します。
- タンニン酸…収斂作用(引きしめる)
- ベルベリン…抗菌作用
木クレオソート
木クレオソート(もくクレオソート)と読み、腸にとって、役に立つ作用が多いのが特徴です。
- 腸内殺菌作用
- 局所麻酔作用
- 過剰な腸管運動を正常にする作用
- 水分、電解質の分泌をおさえる作用
第2章の復習になりますが、水分・電解質の調整は大腸でおこなわれます。
下痢が長引くと、その水分や電解質が失われ脱水症状の原因となるんですよね、、
ちなみに、木クレオソートは正露丸のメイン成分です。
一般的に知名度の高い下痢止め薬ですが、整調成分のアセンヤク、止瀉成分のオウバクも配合されています。
「木クレオソート」の名前の小ネタ
勉強の息抜きの小ネタを1つ紹介。
木クレオソートがなぜ「木」クレオソートなのか、知ってますか?
クレオソートには、
原木を精製した木クレオソートと、石炭を精製した石炭クレオソートの2種類あります。
「医薬品に使える成分」では木クレオソートが配合されており、石炭クレオソートは「工業用の防腐剤」として使用されているんです。
両方とも同じ「クレオソート」ですが、用途がぜんぜん違うんですよ。
そのため、医薬品用の成分は「木クレオソート」と呼ばれて、「木」の文字がくっついているんですね。
木クレオソートについては、正露丸を発売している大幸薬品の公式サイトで解説しています。
» 正露丸・セイロガン糖衣Aの主成分 木クレオソートについて(外部サイト)
吸着成分
吸着成分は、腸管内の異常発酵などで生まれた有害な物質を吸着する成分です。
これだけ種類があります。
- 炭酸カルシウム
- 沈降炭酸カルシウム
- 乳酸カルシウム
- リン酸水素カルシウム
- 天然ケイ酸アルミニウム
- ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム
- カオリン
- 薬用炭
ややこしい名前ですが、聞き馴染みのある「カルシウム」「アルミニウム」と省略して覚えてOKです。
カオリンは天然の粘土(鉱物)で、主成分が含水ケイ酸アルミニウムなので、吸着成分として作用します。
薬用炭は、薬として使用される炭のこと。
ニオイを取る防臭炭と同じ原理で、吸着作用があります。
瀉下成分
瀉下成分は、腸の内容物を排出するための成分です。
瀉下成分は種類が多く、作用も微妙にちがったりします。
- 小腸刺激性瀉下成分
- 大腸刺激性瀉下成分
- 無機塩類
- ジオクチルソジウムスルホサクシネート
- マルツエキス
瀉下薬にはさまざまな種類がありますが、複数の瀉下薬との併用は禁止です。
(いろんな種類の下剤を一緒に飲むのがダメ)
激しい腹痛や下痢などの副作用が起こりやすくなります。
小腸刺激性瀉下成分
小腸刺激性瀉下成分は、小腸を刺激して便を排出します。
即効性があり、細菌性食中毒など早めに体外に出したい時に使用されたりします。
登録販売者試験では、小腸刺激性瀉下成分は「ヒマシ油」だけです。
ヒマシ油は急激で強い作用があるだけに、禁止事項が多いです。
- 激しい腹痛がある人
- 悪心、嘔吐のある人
- 3歳未満の乳幼児
- 妊婦、授乳中
- 脂溶性物質中毒の人
- 駆虫薬との併用
そして数少ない年齢制限がある成分でもあります。
※年齢制限のある薬については、この記事でくわしく解説してます
» 【登録販売者試験】年齢区分の覚え方・年齢制限のある成分一覧
「ヒマシ油、いつ使うの?」という話ですが、ヒマシ油は誤飲や誤食などの中毒に使われたりします。
しかし脂溶性の防虫剤や殺鼠剤(ネズミ用薬剤)による中毒は、有効成分がヒマシ油に溶けてしまい中毒症状を悪化させてしまうので使用禁止です。
【小ネタ】ヒマシ油、現場であまり使われない
ヒマシ油と駆虫薬の併用禁止についてですが、実際の現場駆虫薬は滅多に使わないんですよね、、
ヒマシ油もドラッグストアで売ってますが、買う人はほとんどいないです。
現場でほぼ使わない知識ですが、試験本番や過去問に出てきます。
「試験対策用の知識」として覚えてください。
そもそも、ヒマシ油も一般的に瀉下目的で使うこと自体めったにないんです。
それでも試験ではわりと出題されます。
余談ですが、
ヒマシ油を美容目的や腸内デトックスのために使用する人がまれにいます。
本来の使い方ではないので、健康被害が出る場合があります。
もしあなたの実際の現場に現れたら、適切な対応をしてあげてください。
大腸刺激性瀉下成分
大腸刺激性瀉下成分は、大腸を刺激して反射的に腸の運動を引き起こします。
小腸を刺激するヒマシ油とまちがえないように。
(ひっかけ問題でよく出る)
大腸刺激性瀉下成分は、生薬を含めると数が多いです。
- センノシド
- ビサコジル
- カサントラノール
- ピコスルファートナトリウム
- センナ
- ダイオウ
- アロエ
- ジュウヤク
- ケンゴシ
まちがえやすい名前だと
センノシドは成分名、センナは生薬名です。
つまり、センナ(生薬)にセンノシド(成分)が含まれています。
センノシドの注意点として、センナの茎などを使った製品(食品)と、瀉下薬を同時期に摂取しないよう注意する必要があります。
瀉下成分をダブルで飲まないように、ということですね。
実は医薬品のお茶コーナーに、健康茶としてセンナ茶が置いてあります。
そのため、瀉下薬と併用しがちだったりと、意外と気づきにくいです。
山本漢方センナはセンナ茶の1つですが、健康茶ではなく医薬品で、しかも指定第二類医薬品です。
また、センノシド、カサントラノール、ピコスルファートナトリウムは、大腸の腸内細菌によって分解 → その分解物が大腸を刺激します。
ビサコジルは作用が少し異なり、成分が直腸などの粘膜を直接刺激します。
そして、結腸での水分の吸収をおさえるので、自然なお通じにしてくれます。
センナ、センノシド、ダイオウ、カサントラノールは、授乳中は禁止です。
成分がおちちに移行して、赤ちゃんが下痢をします。
基本的に、妊婦や赤ちゃんに対して瀉下成分は禁止です。
ちなみに、腸の薬は腸溶性製剤が多く
胃で溶けずに腸で効くように考えられて作られています。
例えば、コーラックという市販薬のメイン成分はビサコジルです。
注意事項に、制酸成分を含む胃腸薬や牛乳の摂取を避ける表記がされています。
コーラックと牛乳を一緒に飲んでしまうと、腸で溶けずに胃で溶けてしまうため、薬の効き目がなくなります。
またヒマシ油と大腸刺激性瀉下成分は、どちらも腸粘膜への刺激が強いため、大量に使うのもダメです。
瀉下薬(下剤)としては、かなり効き目が強いため腹痛が起こる場合があります。
コーラックも、わりとお腹が痛くなる下剤です。
刺激性の瀉下薬は、効果がおだやかな便秘薬が効かない場合の、最終段階の手段として、使用することが多いです。
(次に紹介するのが、おだやかな便秘薬)
無機塩類
無機塩類は、腸内容物の浸透圧を高めることで、糞便の水分量を増やし、腸が動いて大腸を刺激します。
- 酸化マグネシウム
- 水酸化マグネシウム
- 硫酸マグネシウム
- 硫酸ナトリウム
マグネシウムは、消化管からあまり吸収されませんが、一部が腸で吸収されて尿から排泄されます。
大量摂取したり腎臓が弱っていると、高マグネシウム血症を引き起こす場合があるので、腎臓病の人は相談する必要があります。
(テキストに書いてありませんが、高齢者も消化管の機能が衰えているので注意が必要)
また、硫酸ナトリウムは心臓病の人が服用する場合は相談が必要です。
血液中の電解質のバランスが損なわれ、心臓の負担が増加し、症状が悪化する場合があるためです。
無機塩類は、刺激性瀉下成分よりお腹が痛くなく、効き目がおだやかです。
そのため、「酸化マグネシウムの下剤=痛くない便秘薬」として知名度が上がりつつあります
ちなみに、酸化マグネシウムは薬学業界では「カマ」と呼ばれています。
(酸化マグネシウム→ 化マ → カマ)
病院でよく処方されるので、調剤薬局では定番の薬です。
また、無機塩類は服用時に水分を多めに取ると、便が出やすくなります。
酸化マグネシウムE便秘薬などの下剤を欲しがっているお客さんに、教えてあげてください。
膨潤性瀉下成分
膨潤性瀉下成分は、腸内で水分を吸収して糞便に浸透させ、容積をかさ増しして柔らかくします。
膨潤性瀉下成分は、以下の3種類です。
- カルメロースナトリウム
- カルメロースカルシウム
- プランタゴ・オバタ
「膨潤性瀉下成分」と聞くと難しそうですが、食物繊維のようなはたらきをする成分です。
そのため、水分を多めにとると、効果が高まります。
市販薬だと、新ウィズワンがありますね。
主成分は、プランタゴ・オバタです。
新ウィズワンの公式でも、薬と一緒にコップ1杯の水(ぬるま湯)で服用することが推奨されています。
DSS(ジオクチルソジウムスルホサクシネート)
ジオクチルソジウムスルホサクシネート、覚えるのに苦労する成分名の1つです。
成分名の中でもトップクラスに長いため「DSS(ディーエスエス)」と省略されます。
英語で表記すると「Dioctyl Sodium Sulfosuccinate」なので、DSSですよ!
(ジオクチル ソジウム スルホサクシネート)
このDSSという成分は、水分を浸透しやすくし、水分量を増やして柔らかくします。
上記の膨潤性瀉下成分とほぼ同じですが、こちらは水分量を増やします。
いわゆる、うんこのかさ増しではありません。
市販薬だと、コーラックⅡなどに配合されています。
過去にこんなツイートをしました。
DSSが、医療用で便秘薬以外にも使用されている例です。
【メモ】ジオクチルソジウムスルホサクシネート。医療用では耳垢水(耳の垢を出す薬)があり、薬剤師同士でも知らなかったそう。化学式を説明してもらったけど、私には深すぎる領域なので断念。なぜDSSと略すのかわかったから、それで良し。
— リンネ@多趣味な人、ときどき登販とブログ (@medicamemo) July 23, 2020
登販で必要な知識は湿潤性瀉下成分の便秘薬、コーラックⅡ。 pic.twitter.com/mQqpKrflr5
まぁ難しいですよね。
登録販売者試験に出てくる市販薬では「瀉下成分」として覚えるだけでOKです。
DSS、俳句みたいに575で読むと覚えやすい気がする。
ジオクチル
ソジウムスルホ
サクシネート
マルツエキス
マルツエキスは麦芽糖が主成分で、サツマイモが原料です。
腸内細菌で分解、発酵してガスが発生し、おだやかに作用します。
水飴状でほんのり甘く、糖分なので栄養価も高いため、乳幼児用の便秘薬として活躍しています。
小話ですが、私の職場の仲いい母ちゃんの子どもが赤ちゃんのとき、ひどい便秘でやばかった時にマルツエキスを与えてたそうです。
それくらい実用的に使われています。
ちなみに、麦芽糖と聞いて第2章を思い浮かべた人はすごいですよ。
唾液中のアミラーゼが、デンプンを分解した後の物質の中に「麦芽糖」があります。
まとめ:腸の薬の各成分の注意点が大事
- 細菌性下痢に止瀉薬は、逆に悪化させる
- 生菌成分に腸内殺菌成分は、効果減少する
- 止瀉成分は出すことも大事
- 瀉下薬の注意点を確認する
- 瀉下薬をたくさん使うのは禁止
腸の薬はとても種類が多く、成分の作用も幅が広いです。
頭の中で、専門用語がまざって混乱する場合があります。
(私はそうだった)
ドラッグストアや製薬会社の製品説明を見ると、わかりやすい説明が記載されていたりします。
市販の薬の添付文書も、勉強に有益な情報がたくさん詰まっています。
あなたの気になる、薬の添付文書を調べてみるのも1つの手ですよ。
腸の薬は副作用も多く、他の病気の症状の1つである可能性もあります。
実際の現場では受診勧奨の場合もあるので、知識をおろそかにしたくないカテゴリだったりします。
また、腸と合わせて胃薬も成分が多く、注意点が多いのでおさえておきたいところです。
あなたの勉強のお手伝いになれば、幸いです。