- 第3章:主な医薬品とその作用、難しい。
- 第3章の成分名を覚える、勉強のコツを教えて!
- わかりやすく覚えられる方法があるなら知りたい…
そんなあなたを、お助けします。
この記事では、第3章の成分の覚え方のコツを解説しています。
後半では、第3章の各成分について解説している記事をまとめています。
私は登録販売者としてドラッグストアではたらいている、リンネと申します。
2018年に受験し、独学3ヶ月で1発合格したという小さな経歴があります。
時短で勉強できるノウハウを、このページを見てくれたあなたにこっそり教えますね。
第3章は【薬の作用と成分】がテーマ
第3章は「薬の作用と成分」がテーマになっています。
登録販売者試験の中で1番むずかしく、覚える内容や専門用語がたくさんできます。
ただ、登録販売者という仕事をするうえで、必要不可欠な知識なんですよね。
- どんな薬があるか
- どんな成分があるか
- 身体にどんな作用があるか
- どんな漢方がどんな人に効くか
お客さんからお薬相談があったとき、薬の成分や作用を知らないと、きちんと回答することができません。
「薬の知識がない=登録販売者として不適合」とも言う人もいたりしますね。
きちんと効率よく勉強すれば、成分名や作用は覚えられます。
どうかあなたは諦めずに、第3章の勉強に取り組んでいただきです。
【めっちゃ多い】第3章の試験範囲について
登録販売者試験の第3章は「主な医薬品とその作用」というカテゴリです。
医薬品の成分と作用がメインなので、
登録販売者試験でもトップクラスに難しい章です。
試験範囲は、ざっくりこんな感じです。
- 精神神経に作用する薬
- かぜ薬
- 解熱鎮痛薬
- 眠気を促す薬
- 眠気を防ぐ薬鎮暈薬(乗物酔い防止薬)
- 小児の疳を適応症とする生薬製剤・漢方処方製剤(小児鎮静薬)
- 呼吸器官に作用する薬
- 咳止め・痰を出しやすくする薬(鎮咳去痰薬)
- 口腔咽喉薬、うがい薬(含嗽薬)
- 胃腸に作用する薬
- 胃の薬(制酸薬、健胃薬、消化薬)
- 腸の薬(整腸薬、止瀉薬、瀉下薬)
- 胃腸鎮痛鎮痙薬
- その他の消化器官用薬
- 心臓などの器官や血液に作用する薬
- 強心薬
- 高コレステロール改善薬
- 貧血用薬(鉄製剤)
- その他の循環器用薬
- 排泄に関わる部位に作用する薬
- 痔の薬
- その他の泌尿器用薬
- 婦人薬
- 内服アレルギー用薬
- 鼻に用いる薬
- 眼科用薬
- 皮膚に用いる薬
- きず口等の殺菌消毒成分
- 痒み、腫れ、痛み等を抑える配合成分
- 肌の角質化、かさつき等を改善する配合成分
- 抗菌作用を有する配合成分
- 抗真菌作用を有する配合成分
- 頭皮・毛根に作用する配合成分
- 歯や口中に用いる薬
- 歯痛・歯槽膿漏薬
- 口内炎用薬
- 禁煙補助剤
- 滋養強壮保健薬
- 漢方処方製剤・生薬製
- 漢方処方製剤
- その他の生薬製剤
- 公衆衛生用薬
- 消毒薬
- 殺虫剤・忌避剤
- 一般用検査薬
- 一般用検査薬とは
- 尿糖・尿タンパク検査薬
- 妊娠検査薬
パッと見ただけでも、めちゃくちゃ種類が多いことがわかります。
そして、さらに細かく薬のカテゴリがわかれているんですね。
成分名は約500種類以上あり、それぞれどんな作用があるのか、どんな成分なのかを覚える必要があります。
第3章の難易度:試験で1番むずかしい
第3章は、ぶっちゃけ試験の中でも1番むずかしいです。
覚える用語が多く、専門的な知識を暗記しなくてはいけないんですよね、、
でも第3章をしっかり勉強しないと、合格は無理です。
試験範囲の多さから、苦手意識があったり勉強のモチベーションが下がってしまったりします。
そのため、誰もがみな苦労する分野で、しかも勉強時間も多めに確保する必要があるんですね。
テキストで第3章のところをパラパラ見てもらうとわかりますが、意味不明な用語や漢字・カタカナがめちゃくちゃ多いです。
この魔の第3章を、いかにうまく攻略するかが合格へのカギになります。
【受験者必見】第3章を攻略するためのコツ
受験者のほとんどが苦労する第3章。
そこで、効率よく勉強するためのコツを教えますね。
- 項目が少ないところからやる
- 単語帳、暗記カードをつくる
- 成分一覧表を壁にはる
- ドラッグストアで市販薬を見てみる
項目が少ないところからやる
項目の少ないところから勉強するという方法です。
例えば、第3章の1番最初の項目は「かぜ薬」ですが、ページ数が多めで、成分名も多く出てきます。
「覚えることが多すぎて、やる気が出ない…」と思うのは私も同じ気持ちでした。
そこで、最後のほうにある「一般検査薬」の項目を見てみてください。
おそらくテキスト1〜3ページくらいしかなく、覚える項目もめちゃくちゃ少ないはずです。
これなら今日勉強するだけで、1つの項目を終わらせることができますね。
テキストの好きな項目からやることで、あなたのやる気モチベーションを維持できます。
試験範囲の項目が少なくて勉強しやすいところだと、下記がおすすめです。
【めちゃくちゃ少ない】
- 禁煙補助剤
- 一般用検査薬
- 尿糖・尿タンパク検査薬
- 妊娠検査薬
【わりと少なめ】
- 強心薬
- 高コレステロール改善薬
- 貧血用薬
- その他の循環器用薬
(コエンザイムQ10など)
最終的に全ての項目を勉強するんですが、順番に関しては好きな順でOKです。
登録販売者の勉強で第3章攻略は以下の手順
— YuuMUTSUKI/ブログ「登販部」の中の人 (@YuuMUTSUKI) March 25, 2022
・第3章の暗記項目を「風邪薬」…「禁煙補助剤」「妊娠検査薬」のように「薬」ごとに細分化する。
・覚える量の少ない「薬」から覚える
・そして「覚えた薬」を積み上げていく
試験では第3章は40問。どの薬が正解でも1点。
ならば楽な薬から積み上げる
単語帳、暗記カードをつくる
登録販売者試験向けの単語帳を作る、という勉強法です。
あなたが学生の頃にやったことがあるかもしれませんが、実はそれと同じです。
紙の単語帳だと、文房具やさん・100均の文具コーナーに置いてあるのですぐ手に入れられます。
最近だと、スマホのアプリを活用できますよ。
第3章の成分名だと、こんな感じで作るのもアリです。
- 表…成分名、裏…何の成分か
(例)クロルフェニラミン、抗ヒスタミン成分 - 表…〇〇成分、裏…成分名
(例)ピレスロイド系殺虫成分、ペルメトリン・フェノトリン・フタルスリン - 表…成分名、裏…作用
(例)グアイフェネシン、軌道粘膜からの粘液の分泌を促進する
あなたの覚えやすい内容で、作ってみてくださいね。
【落ちこぼれ】
— はやし@体と本 (@karadatohon) January 3, 2021
何度も間違える問題は自分の弱点を教えてくれる。
3章の医薬品と作用はやっぱりシンドイ。
いまも使う単語帳メーカーでどんどん↓のようなカードを作り、すき間時間を活用しひたすら暗記しました。
合格したけどこの時作ったカードは捨てられない。#登販 #鍼灸学生 pic.twitter.com/22DG6WIdoN
成分一覧表を壁にはる
第3章の成分名は、受験生にとって暗記がむずかしい項目です。
その成分を一覧表にして、壁に貼るというのも1つの手だったりします。
- あなたの部屋
- リビングの壁
- トイレの壁
- 寝室の壁
- 廊下
「成分名を紙に書いて壁に貼る」という方法、意外とやっている人が多いです。
トイレの壁に貼っている人も多く、数分〜数十分のスキマ時間を有効活用できます。
そういえば 去年の今頃 貼ったんだよなぁ
— ひよこまんじゅう 登録販売者 R3合格 (@hiyoko_manjyu_) March 9, 2022
この空間 落ち着くんだけど 笑
漢方に囲まれてる感 好き💕
付箋だから 何かに貼りなおそうかなって思うけど ここが一番勉強するかも🐤🌱#我が家のトイレ#登録販売者#登録販売者令和3年合格 pic.twitter.com/URQ2rxvUpT
明日、登録販売者試験
— きざみん@筋肉プチ育て中 (@Zkizal8kiza) August 29, 2020
早く終わって欲しいような、明日が来て欲しくないような。。
今になって2章に手こずる感。
勉強は若いウチやね(痛感)
トイレの付箋も剥がしました。#登録販売者試験 pic.twitter.com/p6YnBkEROd
私の職場の仲いい母ちゃんは、
漢方を一覧表にまとめてリビングの壁に貼っていました。
第3章だけでなく、あなたの苦手な章の項目を書いて貼るのもOKですよ。
ドラッグストアで市販薬を見てみる
あなたの家・職場の近くには、ドラッグストアがあると思います。
そのドラッグストアで、
実際の市販薬を手にとって見てみるのも実はアリだったりします。
パッケージを見てみると、どの薬にどんな成分が入っているかがわかるので随時勉強できます。
もし成分を見て作用がわからなかったら、自宅に帰って復習するのもアリです。
気になった薬が見つかったら、購入してみるのも1つの手です。
中に入っている(または薬の外装)添付文書は、成分の作用・薬の副作用といった、試験勉強の役に立つ情報がたくさんつまっているんですね。
添付文書は第5章で学ぶ範囲でもあるので、捨てずに取っておくのをオススメします。
初心者登販さんは添付文書みるくせつけると基本のきが覚えられていい気がした
— ずゆ (@_zuyu_) January 5, 2024
↑添付文書は、合格後の実践でも使える
【時短勉強】第3章の成分名を覚えるコツ
第3章では、おもに成分名と作用を覚える必要があります。
成分約500種類を暗記するためのコツを、ここで教えますね。
- 成分名を省略して覚える
- 成分名の共通する語尾同士で覚える
- 語呂合わせを駆使する
① 成分名を省略して覚える
実は、第3章の成分名は省略して覚えることができます。
例えば「クロルフェニラミンマレイン酸」という、抗ヒスタミン成分について見てみましょう。
この成分名の覚えるべきところは「クロルフェニラミン」です。
「マレイン酸」という語句は、ぶっちゃけ覚える必要がないんです。
実際に、ちゃんとした理由があります。
クロルフェニラミンマレイン酸塩の「マレイン酸塩」、クレマスチンフマル酸塩の「フマル酸塩」は、最終的に安定なかたち(塩)になるという意味。
— リンネ@多趣味な人、ときどき登販とブログ (@medicamemo) September 5, 2020
いわゆる修飾語みたいなものなので、覚えなくても大丈夫とのこと。
※隣の薬剤師の意見です
私の友人の薬剤師と、会話していたときに聞いた内容です。
薬学部で教えてくれる知識だそうです。
つまり、登録販売者試験に出てくる「〇〇塩」の部分は覚えなくても試験にほとんど関係ありません。
この名称は覚えなくても大丈夫です。
- マレイン酸塩
- フマル酸塩
- 塩酸塩
- 硫酸塩(りゅうさんえん)
- 硝酸塩(しょうさんえん)
- リン酸塩
- サッカリン塩
- 臭化水素酸塩
- ヒベンズ酸塩
※ 塩(しお)ではなく、塩(えん)と読みます
これらを省略することで成分名で覚える文字数が短くなるので、勉強の時短になります。
カタカナばかりで、成分名が混ざってわからなくなることも減るでしょう。
たとえば、「クレマスチンマレイン酸」という抗ヒスタミン成分があります。
「クレマスチンはマレイン酸か、フマル酸か」といった内容は、出題されません。
(クレマスチンが何の成分なのかは試験に出る)
この場合、「クレマスチン=抗ヒスタミン成分」と覚えればOKです。
ちなみに「塩酸塩についている塩(えん)って結局何?」という質問がたまにあります。
説明がむずかしいので、かんたんに言うと、
「身体に入っても害のない塩状態」というイメージです。
② 成分名の共通する語尾同士で覚える
成分によって、語尾や共通するキーワードがあるんです。
例えば、局所麻酔成分の成分名の後半を見てみます。
- リドカイン
- ジブカイン
- プロカイン
- テーカイン
語尾に〇〇カインと、共通する語句がありますね。
つまり、「〇〇カイン=局所麻酔成分」と関連づけることができます。
他にも、共通する語尾があります。
- 〇〇リン
…アドレナリン作動成分 - 〇〇ミン
…抗ヒスタミン成分 - 〇〇アゾール
…抗真菌成分 - 〇〇ノール
…消毒成分 - 〇〇ゾン、ゾロン
…ステロイド性抗炎症成分 - 〇〇プロフェン
…非ステロイド性抗炎症成分
もちろん、全ての成分に当てはまるわけではありません。
しかし共通点を見つけると問題の選択肢で迷ったときに、消去法をすると確実にちがう成分では間違えないようになります。
補足:成分名の共通点は薬剤師も活用する
成分名の語尾の共通点については、薬剤師国家試験でも活用されています。
例えば、
「〜〜アゾール = イミダゾール系の抗真菌成分」
という内容は薬学部の授業でも習うそうです。
この成分名の語尾の成分名の共通点は、専門用語で「ステム」と呼ばれます。
薬剤師国家試験を受ける薬学生も使っている方法なので、登録販売者試験でも活用してくださいね。
※薬剤師向けの内容ですが、語尾の共通点のある成分について、やんわり解説されています
③ 語呂合わせを駆使する
第3章の成分名と作用を一致させるテクニックが、語呂合わせです。
語呂合わせと言えば、日本史の授業でやったイメージを持つ人が多いと思います。
- 鳴くよウグイス平安京(794年)
- 嫌でごさんすペリーさん(1853年)
「覚えにくい年号は、数字と文章で覚えてしまおう」という、昔からある勉強法の1つです。
これが登録販売者の試験でも、通じる部分があります。
例えば、「ロペラミド」という下痢止めの成分があります。
語呂合わせにしてみると、こんな感じでまるまる覚えることができるんですね。
【15歳のロイくん、下痢ったのね】
- 15歳……15歳未満禁止
- ロ……ロペラミド
- イ……麻痺性イレウス
- 下痢……下痢止め(止瀉作用)
- た……食べすぎ
- の……飲みすぎ
- ね……寝冷え
このように語呂合わせを活用することで、時短勉強ができます。
あくまで登録販売者試験に合格できる勉強法の1つなので、人によって相性があります。
「ゴロを使ったら覚えやすい!」という方向けですね。
覚えやすくてインパクトのある語呂合わせで勉強したいなら、下記の記事をどうぞ。
【受かるコツ】第3章で8割の点数を取る
第3章は登録販売者試験の中でも出題数が多く、40問も解く必要があります。
試験全体で見ると、120問中84点以上取ることが合格条件です。
このうち、第3章でだいたい8割正解できると、合格圏内にグッと近づきます。
つまり、40問中32点以上を目指すということですね。
最初から満点を取る必要はなく、
過去問をやりつつ、じわじわ点数を伸ばしていけばOKです。
私は第3章で8割取ることを目標にしながら勉強していました。
すると登録販売者試験の本番で、第3章では満点の40点を取ることができたため、余裕を持って合格することができました。
もちろん他の章も勉強する必要がありますが、
第3章で高得点が取れるようになると、かなり精神的な余裕ができますよ。
あなたが本番の試験でどれだけ焦るかは、第3章をどれだけ勉強したかによります。
【おすすめ】第3章の試験対策本【医薬品暗記帳】
ここでは「医薬品暗記帳」という本をおすすめします。
第3章の成分に特化していて、成分名・作用・副作用・相談する人など、さまざまな要素がわかるんですね。
さらに生薬・漢方にも特化していて、円グラフやイラストでわかりやすい説明が特徴的です。
自分の家にも届きました
— こたろー@R4登販受験生 (@kamikazekick007) May 27, 2022
医薬品暗記帳
過去問1周したので
過去問2周しながら、これを読もうと
これは市販薬の名前も書いてあるので、
イメージしやすく、とてもGOOD
それと、職場にある消毒薬、良い悪いの見分けができるようになりました https://t.co/ZJOWQtW8Bh pic.twitter.com/2MHIYcNjvo
本を出版している薬剤師の先生たちも、お墨付きの1冊だったりします。
早織先生の@saori_tmaquilla
— 鈴木伸悟(薬剤師 OTC薬のすすめ方 薬局OTC販売マニュアル) (@pharmacist_OTC) May 27, 2022
『医薬品暗記帳』
で勉強してみました
✅生薬・漢方がとてもわかりやすい!
多くの方が苦手とする分野がイラストなどきめ細やかに工夫されています
✅現場からのひとこと
イメージが湧いて暗記・理解しやすい
✅本、分厚くてボリュームあり
第3章攻略におすすめです! pic.twitter.com/TFEuJRSrKV
村松さん @saori_tmaquilla から新刊『医薬品暗記帳』をご恵投いただきました<(_ _)>すごいボリュームなのにひとつひとつ丁寧にまとめられていて、わたしもおもしろく読んでます。試験対策書だけにしておくのはもったいない一冊。つまりは、合格後も売場に置いて活用できる一冊(OvO)!! pic.twitter.com/VUzzRxjZwF
— くすりのkuriedits (@kuriedits) May 28, 2022
- 生薬、漢方が苦手
- 第3章の成分名が覚えられない
- どの部分が大事なのか知りたい
- 合格してからも使える本がほしい
この本1冊だけで合格は厳しいですが、第3章の成分名を覚えるのに重宝します。
メインテキストのおともにどうぞ。
ちなみに、登録販売者試験にも使えて、合格後の実務経験を積むときにも役に立つ本です。
合格後に読むべき本についての記事が気になる方は、下記からどうぞ。
まとめ
第3章は、登録販売者試験で一番しんどくて大変な項目です。
いかに効率よく勉強するかが重要だったりします。
あなたに合ったやり方で、第3章を攻略してくださいね。
ちなみに、第2章の覚え方も別のページにて解説しています。
» 【登録販売者試験】第2章の重要なポイントまとめ【人体の働きを覚えるコツ】
私が2ヶ月の独学で合格した方法をまとめてあるので、参考にどうぞ。
あなたの時短勉強のきっかけになれば、幸いです。
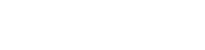



コメント