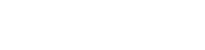- 漢方のことを調べていたら、もっと勉強したくなった。
- イラストや挿絵がある、漢方の図鑑がほしい。
- 一般の人にもわかる漢方薬の本が知りたい。
- 登録販売者、薬剤師向けの本がほしい。
私は現在ドラッグストアで医薬品登録販売者として、お薬相談などの仕事をしています。
よく漢方薬について聞かれるので、漢方・生薬を学ぶために本を探したりしてますが、、
漢方の本、ぶっちゃけ多すぎて何を買えばいいかわからないんですよね。
そこで、一般の方向けにも漢方を勉強するのにおすすめの本を厳選しました。
漢方薬の本といっても、
イラストメインの図鑑・読みやすい本・漢方に特化した専門書など、たくさんの種類があるんです。
そこで「どんな本なのかすぐわかる、✔︎ チェックリスト」をつけました。
あなたの漢方の本探しの参考になれば幸いです。
なお、この記事で紹介している本は
知人から借りたり、実際に読んだ人の感想をもとにオススメしています。
【厳然】漢方薬を勉強できるおすすめ本10冊
ドラッグストア店員の私が、漢方を学べる本を厳選してみたら10冊ありました。
- 漢方薬キャラクター図鑑
- キャラでわかる!はじめての漢方薬図鑑
- 皇帝の漢方薬図鑑
- 生薬と漢方薬の事典
- 読むだけで心と体が元気になっちゃう漢方養生の本
- いつもの食材が「漢方」になる食べ方
- 基本としくみがよくわかる東洋医学の教科書
- 漢方相談便利帖シリーズ(3冊)
上記の本を、まずはざっくりとまとめて紹介しますね。
(ここだけ読んでも大丈夫です)
「漢方薬キャラクター図鑑」について
- オールカラー印刷
- 漢方がゆるキャラ化されている
- イラストメインでわかりやすい
- 児童書なので子供と一緒に読める
「キャラでわかる!はじめての漢方薬図鑑」について
- オールカラー印刷
- 漢方がゆるキャラ化されている
- 漢方薬キャラクター図鑑の大人向け版
「皇帝の漢方薬図鑑」について
- オールカラー印刷
- 和テイストで、日本昔ばなしのような図鑑
- 子供と一緒に読める
「生薬と漢方薬の事典」について
- 生薬と漢方の図鑑ポジション
- 繊細で美しい植物画が特徴的
- 生薬の写真があり、多くの漢方を知ることができる
「読むだけで心と体が元気になっちゃう漢方養生の本」について
- 漢方養生について学べる
- 東洋医学YouTuberロン毛メガネ先生の本
- 体質や体調から、あなたに合う食材が見つかる
「いつもの食材が『漢方』になる食べ方」について
- イラスト多めで読みやすい
- 文庫本サイズで持ち運べやすい
- 気になる症状別の食材や調理法がわかる
「基本としくみがよくわかる東洋医学の教科書」について
- 初学者向けの東洋医学の本
- 漢方と鍼灸(ツボ)について、オールカラーで解説
- 生薬図鑑のカラーポスター付き
「漢方相談便利帖シリーズ」について
- あなたの気になる内容の本を選べる
- 用途別の3シリーズになっている
- ピンクの本
… 漢方の接客に特化
» この本の解説ページへ飛ぶ - オレンジの本
… 漢方163種類の図鑑
» この本の解説ページへ飛ぶ - 赤の本
… 症状からチャートで選ぶ
» この本の解説ページへ飛ぶ
これら10冊が、それぞれどういった特徴があるのか順番に解説しますね。
勉強できる漢方おすすめ本(図鑑)
紹介する本の数が多いので、
①漢方・生薬図鑑 ②初学者向け ③中級者向けにわけました。
あなたがどんな漢方薬の本を見つけたいか、参考にしてくださいね。
まず紹介するのは、漢方・生薬図鑑です。
- 漢方薬キャラクター図鑑
- キャラでわかる!はじめての漢方薬図鑑
- 皇帝の漢方薬図鑑
- 生薬と漢方薬の事典
漢方薬キャラクター図鑑
「漢方薬キャラクター図鑑」は、2016年に発売された本です。
漢方がキャラクターになっていて、とてもカラフルで絵やイラストがたっぷり入っています。
すべての漢方紹介ページに、向いている体質や効能が書かれているんですね。
葛根湯・防風通聖散などの有名な漢方も、どんな人が使うと効果があるのかなど、しっかり学べます。
私は視覚優位脳なので、勉強は耳で聞くより、文字や絵で見ると記憶に残り易いです。
— ファンシー部長 (@fancybucyou) March 4, 2019
で、登販とりたてで漢方が全部同じに見えた時、この本読んだら薬が擬人化されていて、わりとすんなり覚えていけました。
子どもに薬飲ませる時にと思って買ったけど、仕事にも役立ってます😁漢方苦手さんにお勧め! pic.twitter.com/NLQSBvd18y
実は子ども向けの本だったりします。
文章にふりがなが振ってあり、難しい漢方名も読めるように工夫されているのがポイントです。
それでも紹介されている漢方は52種類と、児童向けにしてはがっつり紹介されているんですよね。
漢方・生薬の基礎や基本的な考え方が、キャラクターでゆるく解説されているので、ちょっとした息抜きに読むのに適している本だったりします。
最近だと、登録販売者の試験を受験する人に好評だったりします。
(市販の薬を販売できる資格です)
漢方・生薬の勉強になると話題になっていて、私の周りでも、実際に読んでいる人が多かったりします。
ちなみに児童書なので、ふりがなが多いのも特徴です。
絵で見て覚えるのもよし、子どもと一緒に絵本感覚で読むのも良しなので、この1冊で活用できます。
✔︎ イラストやカラーページの本が読みたい
✔︎ 漢方の基礎がゼロでもわかりやすい
✔︎ 自分にぴったりの漢方を見つけたい
✔︎ 子どもと一緒に読んで学びたい
キャラでわかる!はじめての漢方薬図鑑
2021年3月に発売された本で、先ほど紹介した「漢方薬キャラクター図鑑」の続編なポジションの本です。
そのため児童書ではなく、とてもわかりやすい大人向けの本といった感じです。
キャラクター図鑑より、ふりがなが少ないのでスラスラ読めます。
『はじめての漢方薬大図鑑』読んだ〜。中華ものが好きな私としては、漢方が気になるのです。あれって何だろうとか。ゆるキャラ多めで読みやすい😊 ただ生薬の原料って、不思議なものが多いですね。竜骨は、哺乳動物の化石化した骨って、ええっ!?
— さとう たつき (@satohtatsuki) February 10, 2023
各キャラクターが語り手になって話しかけてくるような文章なので、漢方のキャラと内容がイメージしやすいんですよね。
一般の方だけでなく、医療系資格者(登録販売者・薬剤師・鍼灸師など)にもおすすめできる1冊です。
『キャラでわかる!はじめての漢方薬図鑑』
— プラナ松戸治療室【自律神経系・心療内科系鍼灸院】JR武蔵野線新八柱駅・新京成線八柱駅徒歩3分 (@BAw63R4aUPqfqXg) April 3, 2021
代表的な漢方薬の特徴がキャラクターで描かれていて理解しやすい。また似た漢方薬(六君子湯と四君子湯など)の使い分けも平易に解説されていて漢方薬選びにも重宝する。一般の方のみならず漢方初学の薬剤師、登録販売者、鍼灸師などにもお薦め。 pic.twitter.com/VidTOzW2cl
本の内容に大幅な変更はないので、
キャラクター系の漢方本で迷っているならこちらをどうぞ。
Amazonのプレビューで、本の内容が少し読めます。
皇帝の漢方薬図鑑
「皇帝の漢方薬図鑑」は、2017年に発売された本です。
イラストがかわいく、日本昔ばなしのようなイメージで読むことができるんですね。
以前Twitterで話題になってた「王子様のくすり図鑑」
— 遼-Haruka- (@sol_terra_luna) November 4, 2019
買いに行ったら「皇帝の漢方薬図鑑」ていうのもあって。
買うよね。
王子様は子供向けの薬だからかRPGぽかったけど漢方薬は日本昔ばなしみたい。可愛い。
「王様のくすり図鑑」もあるらしい。欲しい。 pic.twitter.com/cWaJIZaKkk
どの漢方がどの症状(かぜ・胃の不調など)に効くかが、イラストでわかります。
登録販売者試験の勉強用として、使ってみるのも1つの手です。
良い点
— ハル@R3登録販売者合格㊗️🌈 (@touhan8haru) August 18, 2021
✔︎漢方の基本が詳しく載っている
✔︎効能効果が手引きの文で載っているものもある
✔︎ポイントがわかりやすい
✔︎生薬についても画像付きで載っている
悪い点
✔︎先に症状ごと名前だけまとまっていて、後半に50音順になっているから見にくい
✔︎副作用が試験範囲外まで書かれている pic.twitter.com/RUedoLGOe9
漢方の内容がメインなので、生薬についての内容は少なめです。
✔︎ イラストやカラーページの本がいい
✔︎ 子どもと一緒に読んで学びたい
✔︎ 漢方の基礎がゼロでもわかる
✔︎ 和テイストの図鑑がほしい
漢方薬図鑑もイラストメインの本なので、視覚的にわかりやすいのが特徴です。
生薬と漢方薬の事典
「生薬と漢方薬の事典」は、2020年3月に発売された本です。
この本の1番のおすすめポイントは、本の表紙にもなっている生薬の植物画なんですね。
漢方がどんどん面白くなってきて、こんな本を買う私になってしまった。
— Teety-woo (@WooTeety) June 28, 2021
生薬のもとの植物の姿が美しい細密画で載っていたり、漢方の基本的な考え方から漢方薬の成分や効き目、どこから眺めても読んでも楽しい。
表紙と裏表紙もすてきー。
「生薬と漢方薬の事典」
田中耕一郎 編著 / 日本文芸社 pic.twitter.com/ZdGtqXaBj4
とても綺麗で繊細な植物が描かれていますよね。
生薬の元となっているのは、大半が植物です。
この本では、花・果実・葉っぱ・根っこなどの生薬の本となる植物画が、とても美しく、細かい描写で描かれています。
リアルな写真も印刷されているので、両方合わせて生薬のイメージがしやすくなっていますね。
その数、なんと119種類あります。
パラパラめくって見るもよし、じっくり細かい絵を観察するもよし、です。
生薬だけでなく、漢方薬の項目も充実しています。
適応症状、体質、分量、出典などを紹介していて、なんと298種類もあります。
漢方のページをめくると、見たことのない漢方名がどっさり出てきます。
登録販売者を受験予定なら、どんな見た目なのかイメージがつきやすいので
生薬・漢方の勉強に生かすことができます。
「生薬と漢方薬の事典」という表題そのままの本ですが、個人的には「生薬図鑑」というイメージです。
どんな症状の時に使用すべきがといった漢方の説明が物足りないかもしれません。
あなたが植物画、生薬の写真、漢方の種類を目で見て知りたいなら、この本がオススメです。
✔︎ 漢方・生薬の図鑑が欲しい
✔︎ 生薬の植物画・写真が見たい
✔︎ 生薬と漢方の両方を勉強したい
✔︎ たくさんの漢方の種類を知りたい
ちなみに、この本の植物画を描いている「やまだえりこさん」はプロの絵の先生です。
名古屋で絵画教室を開いているので、気になる方はご覧ください。
以上、漢方・生薬図鑑の紹介でした。
イラスト系の図鑑は、絵のタッチによって好みがわかれます。
あなたの好きな漢方・生薬図鑑を選んでくださいね。
勉強できる漢方おすすめ本(初学者向け)
イラストばかりの図鑑は物足りない、でも専門用語ばかりの本は嫌だな…
そんなあなた向けの本はこんな感じの内容です。
- 不健康な生活を見直したい
- もっと気軽に漢方を取り入れたい
- いつもの生活でできることを知りたい
漢方=薬だけではありません。
いつもの食生活を少し意識する「養生」でも、体質が改善します。
普段のスキマ時間でも活用できるように、イラストがあったりカラー印刷の読みやすい本をまとめました。
読むだけで心と体が元気になっちゃう漢方養生の本
2022年12月に発売された本です。
著者は「漢方養生指導士・国際中医薬膳管理師・国際中医専門員」の肩書をもつ「ロン毛メガネ」先生。
名前こそインパクトがありますが、香港人で漢方のスペシャリストです。
漢方の専門書というより「いつもの生活でできること」に焦点をあてています。
食べ物とメンタルが繋がっていることや、生活習慣についてのポイントを教えてくれるんですね。
本の中でも、特に印象的な見出しはこんな感じ。
- 繊細な日本人、鬼強い香港人
- 「気」と「血」は、ラブラブなカップル♡
- 日本人に「冷え性」が多いわけ
- 香港式・命を養うスープ養生
- 季節の変化に合わせて、養生も変わる
- 「いい言葉」は天然のサプリメント
イラストや挿絵はそこそこに、
ロン毛メガネ先生の優しくも力強い語り口調で、気持ちのこもった読みやすい本です。
✔︎ 食材の特性を知りたい
✔︎ 漢方専門家の本がほしい
✔︎ 不健康な生活から脱却したい
✔︎ 自分の体質に合った養生を勉強したい
YouTubeやX (旧twitter)をメインに活動されているので、気になる方はチェックしてみてください。
いつもの食材が「漢方」になる食べ方
2023年9月に発売されたばかりの新書で、中医学を学んだ櫻井大典先生の最新本です。
本の内容はこんな感じです。
- 漢方の基本的な考え方(気血水)
- カゼ、病気に効く食材&食べ方
- 疲れ、だるさに効く食材&食べ方
- 冷え、美容に効く食材&食べ方
- こころに効く食材&食べ方
- 体質タイプ別食べ方
食材の属性や効能、それについて効果的な食べ方(調理法)を解説しています。
難しいレシピはほとんどなく、どれも普段の料理で実践することができます。
カラー印刷で見やすく、マンガ形式でわかりやすい内容も特徴的です。
ネットでのクチコミの評価も高く、
私生活に漢方・養生を身近に感じることができる本ですよ。
文庫本サイズで持ち運びやすいので、通勤途中や外出のおともにどうぞ。
✔︎ 漢方専門家の本がほしい
✔︎ カバンに入るサイズの本がいい
✔︎ 普段の料理+養生を組み合わせたい
✔︎ 症状にあった食材とレシピが知りたい
櫻井大典先生は他にも本を出版しているので、あなたの興味のある本をどうぞ。
» 予約の取れない漢方家が教える:病気にならない食う寝る養生
勉強できる漢方おすすめ本(専門家向け)
こちらは中級者向けの内容がメインの本です。
登録販売者・薬剤師・鍼灸師など、専門職の人向けの内容で、より勉強したい人におすすめです。
- 基本としくみがよくわかる東洋医学の教科書
- 現場で使える 薬剤師・登録販売者のための漢方相談便利帖(ピンクの本)
- 現場で使える 薬剤師・登録販売者のための漢方相談便利帖 わかる!選べる!漢方薬163(オレンジの本)
- 現場で使える 薬剤師・登録販売者のための漢方相談便利帖 症状からチャートで選ぶ漢方薬(赤の本)
専門用語をわかりやすく解説していたり、より深く学べるための本をまとめています。
基本としくみがよくわかる東洋医学の教科書
「基本としくみがよくわかる東洋医学の教科書」は、2014年に発売された本ですが、今でもたくさんの方に読まれています。
ロングセラーの理由は、
初学者向けなのに幅広い内容を勉強できるところですね。
まず陰陽論・五行論などの中国の自然哲学思想を解説しています。
五臓六腑(基礎知識)についてイラストや図解でわかりやすく説明しているので、初心者でもイメージしやすいのが特徴です。
また、漢方だけでなく鍼灸の知識も勉強できるんですね。
そう、この本は「東洋医学を学べる本」なので、鍼灸(しんきゅう)の知識も合わせて知ることができます。
「鍼灸=はり・お灸」というイメージですが、
この本では、どのツボがどこに効くのかがわかります。
自宅でこの本を見ながら、良さげなツボを探すのもアリですよ。
文章についても、難しい漢字はふりがなが振ってあったり、各ページのところどころに用語解説がされています。
ちなみにオールカラー印刷なので、どのページを開いてもカラフルです。
最後のページに索引もあるので、
気になる用語もすぐに探せるのがありがたいポイントですね。
さらにさらに、本の最後の表紙にふろくのカラーポスターがついています。
「経穴MAP&生薬図鑑」を、壁に貼って少しずつ覚えていくのも1つの手ですよ。
鍼灸に興味がなくても、漢方だけでも基礎が勉強できます。
おはようございます。
— 月野 (@tukitukiko229) October 24, 2021
漢方の勉強をしてると出てくるのが気、血、津液や五行、五臓が表される色体表。難しい(・д・`;)
イラストを切って貼ってコピーしてみましたが数年間放置してたこの本を思いだしました( ゚д゚)ハッ!
朝のスペースで知識が増えた今ならこの本が理解出来る!頑張るぞー💪 pic.twitter.com/jhIKTE77en
ふろくがたくさんついている本書。
最初は少しむずかしい内容だと感じるかもしれませんが、何回も読むうちに理解できるようになります。
✔︎ 東洋医学について気になっている
✔︎ カラー印刷で読みやすい本が欲しい
✔︎ 身体のしくみを中医学目線で見たい
✔︎ 漢方と合わせて鍼灸の知識も気になる
文章が各ページにみっちり詰まっているので、人によっては圧迫感があって少し読みにくいかもしれません。
ですが、オールカラー印刷・比較的わかりやすい説明が多いので、
東洋医学をひととおり学びたい人におすすめです。
現場で使える 薬剤師・登録販売者のための漢方相談便利帖
漢方相談便利帖シリーズの第1弾で、2018年3月に発売されました。
ピンク色の表紙が特徴です。
漢方の基礎が上手にまとめられていて、
これから漢方の知識を身につけたい人向けの内容となっています。
漢方の用語から中医学で考えられる病態・原因など、初心者目線で書かれているんですよね。
おもな生薬の性質や薬効、漢方薬の処方についても、くわしい解説があるので、それぞれ見比べることができます。
また、漢方のカウンセリング技術を上げるための項目にも注目です。
- 漢方の健康相談の流れ
- 聴き取りで大切な3つのポイント
- 証を見極めるために確認すること
- 相手に伝わるアドバイスの仕方
漢方の接客方法に特化しているので、あなたの職場でも応用することができます。
漢方の基礎知識 → 生薬・漢方の勉強 → 漢方のカウンセリング方法と、段階を踏んで成長できる本です。
生薬と漢方の解説では、登録販売者試験に出てくる範囲とけっこう被っているため、漢方を勉強するテキストとしても活用できます。
専門用語をわかりやすい言葉に直してあったりと配慮されていますが、挿絵やイラストがほとんど無いのが難点かもしれません。
気軽に読む本としては向いていませんが、漢方の専門書としては良き1冊です。
おそばせながら「タクヤ先生」の本を手に入れました。
— 漢方薬 局太陽堂🔥フォロワー1万人で絵本を出版🔥 (@taiyodo_kampo) October 30, 2018
専門者はもちろんのこと、漢方を少し知っている人でも教科書として活用できる素晴らしい書籍だと思います(^^)
漢方が深く学べていない薬剤師、登録販売者の方にはオススメです✨#タクヤ先生 #スギヤマ薬局 pic.twitter.com/5Xlnym7Ayf
✔︎ 漢方を基礎から勉強したい
✔︎ 漢方を勉強するコツが知りたい
✔︎ 生薬・漢方のくわしい解説が知りたい
✔︎ 仕事で漢方相談ができるようになりたい
漢方の本の中でも漢方の接客に特化した内容です。
ドラッグストア・薬局で働く人に、おすすめしたい1冊です。
現場で使える 薬剤師・登録販売者のための漢方相談便利帖 わかる!選べる!漢方薬163
漢方相談便利帖シリーズ、第2弾で、2018年12月に発売されました。
オレンジ色の表紙が特徴です。
おはようございます。
— 土屋幸太郎@土屋薬局 山形県東根市|薬剤師・不妊カウンセラー|子宝と更年期のための女性の漢方養生 (@tutiyak) December 18, 2018
タクヤ先生(@takuyasensei )の著作 「現場で使える薬剤師・登録販売者のための漢方相談便利帖 わかる!選べる!漢方薬163」が発売されました!
ワンポイントメモは参考になりますし、参茸補血丸など中成薬の詳しい解説もお見事です。
皆さま、ぜひご購入を検討下さいね! pic.twitter.com/48kKzb4OoV
この本は気血水・陰陽・五臓六腑(ごぞうろっぷ)といった、漢方や中医学の基礎的な内容が収録されています。
血虚や水滞などの9つの病態が具体的な症状で説明・解説しているので、どのような状態なのか想像しやすいのがポイントですね。
この本のメイン項目は、知っていると便利な漢方薬の項目です。
漢方の種類がとても豊富で、なんと163種類も掲載されています。
(本のタイトルの163はそれです)
たとえば、登録販売者の試験範囲の漢方は78種類くらいですので、2倍以上も知識を得ることができます。
市販では売っていない、マイナーな漢方も存在しますしね。
この本は、それぞれの漢方がどんな症状・どんな体質に効くのか一目でわかります。
さらに、ワンポイントメモも書かれていて、漢方と症状のイメージがしやすくなっているのもありがたいところ。
漢方が効くしくみ、似た作用同士のの漢方比較など、かゆいところに手が届く内容も知ることができます。
基礎的な内容も書かれていますが、ほとんどが専門用語ばかりです。
挿絵も少なく、理解するのに時間がかかるかもしれません。
漢方の種類がとても多いので、漢方辞典のように使用できる本です。
(索引がないので、ふせんを貼って使うのをおすすめします)
✔︎ ずっと使える漢方の辞典がほしい
✔︎ 漢方で似た作用同士の比較が知りたい
✔︎ 気血水・陰陽・五臓六腑などを学びたい
✔︎ 漢方が好きで、たくさん種類を覚えたい
パラパラめくって、気になる漢方をとりあえず勉強するのもアリです。
現場で使える 薬剤師・登録販売者のための漢方相談便利帖 症状からチャートで選ぶ漢方薬
漢方相談便利帖シリーズ第3弾で、2020年8月に出版された新しめの本です。
赤色の表紙が特徴です。
漢方のスギヤマ薬局(@takuyasensei)のタクヤ先生で有名な杉山先生が新しく著作「現場で使える薬剤師・登録販売者のための漢方相談便利帖 症状からチャートで選ぶ漢方薬」を出版されました。
— 土屋幸太郎@土屋薬局 山形県東根市|薬剤師・不妊カウンセラー|子宝と更年期のための女性の漢方養生 (@tutiyak) August 21, 2020
更年期症状、貧血、尿トラブル、物忘れ・認知症症状など気になる漢方がチャートで分かる!
お勧めですよー pic.twitter.com/SdZdP6Imxd
症状や体質から、あなたや相談者に適した漢方薬をフローチャートで探し出すことができます。
フローチャートとは、複雑な選択肢などを、図形や矢印で視覚的にとらえることができる手法です。
心理テストで「はい・いいえ」の質問に答えるようなイメージでいけます。
フローチャートで見てわかりやすく、症状別に適切な漢方を選べることが、他の漢方相談便利帖シリーズと異なる点です。
主症状+副症状+体質から、1番ベストな漢方を絞り込むことができるので、他の本にはない特徴ともいえますね。
先ほど紹介した「わかる!選べる!漢方薬163」(オレンジの本)と内容がリンクしているため、一緒に使う前提で発売された本です。
2冊合わせて使うことで、より一層知識が増えます。
ただ、両書とも少しサイズが大きめなので、持ち運ぶにはかさばるかもしれません。
「現場で使える漢方相談便利帖」シリーズの中では、1番実践的に使える内容です。
✔︎ 信用性のある新しい本がほしい
✔︎ 漢方と症状を一致させて覚えたい
✔︎ 症状からお客さんに合う漢方を選びたい
✔︎ 漢方の基礎〜実践まで、ひと通り学びたい
以上が、新人登録販売者便利帖シリーズです。
難点をあげるとしたら、3冊とも正方形で少し大きめなので場所を取ります。
ぶっちゃけると、便利帖シリーズはかなり専門的な内容となっています。
初学者向けというより、薬剤師目線というのもあるかもしれません。
そのため、漢方初心者にとってはレベルの高い本だと感じる方も多いようです。
しかし、漢方が大好き・もっと専門的な東洋医学の知識を勉強したい人に、全力でオススメできる本シリーズです。
まとめ
ここまで読んでくださって、ありがとうございます!
漢方は一見難しそうに見えますが、
勉強すればするほど楽しくなる、とても奥が深い学問です。
カタカナばかりの成分の参考書より、漢字で埋め尽くされている漢方や生薬の書籍のほうが好きな人もたくさんいます。
この記事では、ドラッグストア業界で人気な本を厳選して紹介しました。
もちろん、ここで紹介した10冊以外にも魅力的な本はたくさんあります。
Amazon・楽天市場などのネットショップで、本を探してみるのも手段のひとつです。
そうすることで、あなたにの読みたい・役に立つ本が見つかりやすくなります。
漢方に関する本は、どれも個性があります。
「何となく買った本、難しすぎて読めない」
なんてこともあるため、選ぶときはあなたが興味のある本をどうぞ。
リプライありがとうございます😊
— さめちゃん🍭漢方薬店お手伝さん (@same_chan_97) July 21, 2021
お客さんにあったものとかを選ぶ際には
「現場で使える 薬剤師・登録販売者のための漢方相談便利帖 わかる!選べる!漢方薬163」
「薬局で買える漢方薬のトリセツ」
写真でいう左の2冊ですね。
写真にはないですが「漢方薬キャラクター図鑑」とか読みやすいかもです! pic.twitter.com/KkNGYw8OuY
タクヤ先生 @takuyasensei の新刊
— 早川コータ Podcast『コータの漢方RADIO』毎日配信中 (@sawatayaph) August 20, 2020
桃色本、橙色本に続き『赤色本』が登場です😊
絶賛予約中なので漢方を勉強したい薬剤師や登録販売者の方は今回の新刊も必携です〜まだの方は3冊まとめてGO‼️
病名で漢方を選ぶマニュアル本でなく『証』で分類しながら症状が起こる仕組み、養生まで網羅されてます😆 pic.twitter.com/i6riLbYKXY
この記事が、あなたの人生の学びのきっかけになれば幸いです。
✔︎ 漢方・生薬図鑑
» 漢方薬キャラクター図鑑
» キャラでわかる!はじめての漢方薬図鑑
…オールカラー&イラストでわかりやすい
» 皇帝の漢方薬図鑑
…日本昔ばなしのような図鑑
» 生薬と漢方薬の事典
…キレイな植物画の生薬図鑑
✔︎ 初心者向けの勉強本
» 読むだけで心と体が元気になっちゃう漢方養生の本
…東洋医学YouTuberの最新巻
» いつもの食材が「漢方」になる食べ方
…症状別に食材&食べ方がわかる
✔︎ 専門家向けの勉強本
» 基本としくみがよくわかる東洋医学の教科書
…漢方と鍼灸(ツボ)
» 漢方相談便利帖(ピンクの本)
…漢方の接客方法が学べる
» わかる!選べる!漢方薬163(オレンジの本)
…163種類の豊富な漢方辞典
» 症状からチャートで選ぶ漢方薬(赤の本)
…チャートで症状から選べる
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このサイトでは漢方の本だけでなく、独学でも取れる医療系資格についても詳しく解説しています。
気になる方は、下記をどうぞ。
» 【独学OK】学校に通わなくても取れる医療系資格まとめ【おすすめ】
あなたが登録販売者として、実践的な知識を学びたいなら下記の記事をどうぞ。
» 【厳選】現役の登録販売者が選ぶ、実務経験におすすめの本まとめ(未経験OK)
あなたのお役に立てたら幸いです。