- 学校に通わなくても取れる、医療系資格が知りたい
- どんな医療系資格があるのか調べている
- 自宅で勉強して資格を取りたい
そんな悩みを解決できるヒントを教えますね。
私はここで紹介する医療系の資格を2つ持っているリンネという人です。
(医薬品登録販売者、歯科助手資格)
あなたは将来のために役立つ資格を探していますよね。
学校に通わなくても取れる = 自宅で勉強すれば取れる資格でもあります。
この記事では、実用的で使える5つの医療系資格を教えますね。
| 資格の名前 | 主な職場 | 主な仕事内容 | 通信講座 (ユーキャン) | おすすめ度 | 解説記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療事務 | 病院・クリニック | 受付・会計など | » 公式ページ | » 医療事務について | |
| 調剤薬局事務 | 調剤薬局 | 受付・会計など | » 公式ページ | » 調剤薬局事務について | |
| 看護助手 | 病院・クリニック | 患者のサポートなど | » 公式ページ | » 看護助手について | |
| 歯科助手 | 歯科医院 | 受付・会計・ 診療補助など | » 公式ページ | ※現在記事作成中 | |
| 医薬品登録販売者 | ドラッグストア・コンビニ ディスカウントストア など | 市販薬の販売・健康相談 在庫管理など | » 公式ページ | » 登録販売者について |
結論をいうと、
あなたの気になる資格を取ればOKです。
ぶっちゃけ、どの医療系資格にもメリット・デメリットがあるので…!
あなたが興味を持てる資格が見つかるように、がっつり調べて記事にしてあります。
注意:かなり長文な記事です。
興味ないところは飛ばして、気になるところだけ読んでください
\ 勉強に自信がない人にオススメ /
【はじめに】独学で取れる資格、取れない資格について解説
医療系の資格はざっくりわけて、独学で取れるものと、どうしても取れないものの2種類にわかれています。
たとえば「薬剤師をユーキャンで取れますか?」という質問がたまに来るんですが、ユーキャンで薬剤師の資格を取ることはできません。
薬剤師の資格は、薬学部(薬学科)のある大学で6年間勉強して、国家試験に合格する必要があります。
そのため、ユーキャンのような通信講座で薬剤師資格を取ることは不可能です。
独学でも取れる主な医療系資格は、下記のような資格です。
- 医療事務
- 調剤薬局事務
- 看護助手
- 歯科助手
- 医薬品登録販売者 など
これらの資格は独学や通信講座といった方法で、あなた1人で取得することができます。
反対に、どうがんばっても独学で取れない医療系資格はこんな感じです。
- 医師
- 歯科医師
- 獣医師
- 薬剤師
- 看護師 など
独学で取れない資格は、医療系の大学や専門学校に通う必要があります。
基本的に、資格の名前に「〜師」とつくものは、専門の医療系学校で勉強してから資格を取るイメージですね。
まず「独学で取れるのはどんな資格」なのかを知っておくと、あなたが今後ほしい資格が見つかりやすくなります。
【医療系資格の王道】医療事務の資格
医療事務は、学校に通わなくても取れる医療系資格のなかでも有名な資格です。
3〜4ヶ月という短期間で取れるのもメリットで、年中通して人気な医療系資格の1つだったりします。
さらに、出産後・子育て中の主婦にとっては、再就職しやすい仕事でもあります。
医療事務の仕事について
医療事務のおもな仕事は、病院や個人医院・クリニックなどの受付業務です。
- 受付業務
- 会計業務
- クラーク業務
- レセプト作成業務
受付・会計業務は、病院に行った時の受付の人をイメージすればOK。
患者さんの対応・会計の仕事をしている、あの人たちです。
クラーク業務とは、患者さんと医師・看護師の橋渡しをする仕事です。
カルテの管理・患者さんの誘導・電話対応など、診療をスムーズに進めるための大切な業務です。
最後に「レセプト」という難しい用語がありますが、「レセプト」は、保険者に請求する診療報酬明細書のことです。
あなたは病院に行くと、保険証を出して3割負担でお金を払っていると思います。
レセプト業務とは、残りの7割を保険者(あなたの会社・国など)に請求するための仕事です。
この専門的な仕事を行うための資格が、医療事務というわけですね。
医療事務の仕事の中でも「レセプト業務」が難しそうに見えますが、きちんと勉強することでしっかり対応することができます。
受付対応をしつつ、保険点数を計算したり、パソコン入力をするのがメイン業務です。
医療系資格の中でも、人気だし合格しやすいのも良きポイントですね。
井ノ原さんのユーキャンCM見ると何か学ぼうかなって思っちゃう😌
Ⓜ️ (@mf_maison) January 11, 2021
昔、ユーキャンで医療事務の資格取った時の達成感はよかった😁 pic.twitter.com/EpSfB7qQqU
医療事務の資格の種類
医療事務の資格は、大きくわけて4種類あります。
- 医療事務認定実務者(R)試験
- 医療事務技能審査試験(メディカルクラーク(R))
- 医療事務管理士(R)技能認定試験
- 診療報酬請求事務能力認定試験
医療事務の資格は厳密にはちがいますが、ぶっちゃけると
医療機関にとって、これらの医療事務資格のちがいを区別していなかったりします。
厳密には資格の種類がちがいますが、「医療事務の資格」として一緒にされがちなのが本音です。
医療事務のメリット
医療事務のメリットは4つあります。
実は後に紹介する医療系資格と、メリットがほぼ一緒だったりします。
- 面接で「即戦力」として評価してくれる
- 資格があるという自信につながる
- ブランクがあっても再就職できる
- 資格手当による給料アップ
医療事務の資格は、まず面接のときに役に立ちます。
レセプト業務ができるという即戦力をアピールできるので、人手の足りない医療機関では重宝されやすいですね。
もしあなたが医療業界の未経験でも、
医療事務の資格があることで「未経験・無資格」の人と差をつけることができます。
また、あなたが育児や介護などで仕事現場を離れてしまっても、
医療事務という資格があることで再就職しやすくなります。
過去の経歴を重要視してくれる病院・クリニックもあるので、資格+経歴を面接でアピールできるのもポイント。
ちなみに会社によっては資格手当がつく場合もあって、相場は¥5,000〜¥10,000くらいです。
※ 民間資格なので資格手当がない職場もあります
医療事務のデメリット
メリットの多い医療事務資格ですが、少なからずデメリットがあるので、合わせて紹介します。
- 医療事務の資格は必須ではない
医療事務の資格は、実は必須ではありません。
個人経営の診療所・クリニックだと、業界未経験+無資格でも採用されたりします。
未経験+無資格より、未経験+医療事務の方が面接に通りやすいので、「ないよりある方がいい」というイメージですね。
医療事務をおすすめする人
医療事務の資格をおすすめする人は、こんな感じです。
- 短期間で資格を取りたい
- コツコツ事務作業が好きだ
- 病院の受付の仕事がやりたい
- 出産、子育て後に再就職ができる資格がほしい
シングルマザーの方や転勤族のお母さんに人気で、ぶっちゃけ合格する人も多いです。
いよっしゃああああああ!!
— あーちゃん@ (@athan0908) May 24, 2019
ユーキャンの医療事務の試験合格したぞい! pic.twitter.com/NZ9aWvqQMi
医療事務の資格、合格したぁぁぁ!
— にゅび。 (@nyubi_3) December 15, 2022
勉強したのなんて久しぶり過ぎたけど、色々あるなか、頑張って良かった!
ユーキャン、勉強しやすかった!
#ユーキャン
#医療事務
#資格取得
» ユーキャンで医療事務を調べる(公式サイト)
※ ①医療事務認定実務者(R)試験が受講可能
ユーキャンの通信講座でもいいですが、テキストを自分で買って独学で勉強するのもアリです。
※ 上記は④診療報酬請求事務能力認定試験
医療事務は短期間で取ることができて知名度も高いので、医療系資格の中でも特に人気です。
医療事務について詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。
» 【医療事務】仕事内容・向き不向き・やりがいなど解説!【経験談あり】
【薬が好きならアリ】調剤薬局事務の資格
調剤薬局事務は薬をもらう場所、調剤薬局で役に立つ資格です。
薬が好き・パソコン入力がやりたい・受付業務に興味があるなら、この仕事に向いています。
調剤薬局事務の仕事について
医療事務と同じく、受付や会計などの仕事がメインになります。
医療事務との大きなちがいは、職場が病院ではなく薬局ということです。
- 調剤薬局の受付業務
- 患者さんの接客
- 会計業務
- レセプト作成
- 薬剤師の補助業務
調剤薬局も保険証を使うので、レセプト業務がメインです。
医療事務のように、保険点数を計算したりパソコン入力をします。
もしパソコン操作が苦手でも、医療事務の仕事よりは難しくないそうです。
「ダブルクリックができる・ローマ字入力ができれば大丈夫」と私の友人の薬剤師が言っていました。
レセプト画面のパソコンに慣れれば、比較的やりやすい仕事のようです。
病院ではなく薬局での仕事なので、薬剤師の人と一緒に働きます。
薬剤師は調剤業務(薬を作る仕事)をしている専門職で、薬局のボスとも言える存在ですね。
薬局事務は事務作業だけでなく、
薬剤師のフォローをしたり患者さんとコミュニケーションを取るのも重要です。
薬の入った箱を取ったり、電話対応したり、率先して動けるなら薬局でうまく働けます。
調剤薬局事務は4種類ある
調剤薬局事務の資格もいくつか種類があり、ざっくり4種類紹介します。
- 調剤薬局事務検定試験
- 調剤事務管理士(R)
- 調剤事務実務士(R)
- 調剤報酬請求事務専門士
この中でおすすめなのは、①調剤薬局事務検定試験です。
調剤薬局事務の資格の中でも費用が安く、短期間で取りやすいのがポイントですね。
計算問題が苦手な人でも、合格することが可能です。
ユーキャンの調剤薬局事務講座の添削課題、勉強嫌いで学生時代の数学の計算は合った試しがない私でも何とか基準点クリア🙌✨
— なだゆ@男の子ママ🐘 (@nadayu_1819) August 28, 2020
あとは試験を待つのみ……!! pic.twitter.com/HrigP112cb
ユーキャンの調剤薬局事務講座
— ⋆아이(ai)⋆ (@a7t5s13) May 7, 2017
修了証届いた( ´∀`)
2ヶ月で合格した( ´∀` )b pic.twitter.com/WlnhqCy66H
調剤薬局事務のメリット、デメリット
調剤事務のメリットは、医療事務とほぼ一緒です。
- 面接で「即戦力」として評価してくれる
- 資格があるという自信につながる
- ブランクがあっても再就職できる
- 資格手当による給料アップ
デメリットは、民間資格のため必須ではないということですね。
しかし、調剤事務を持っている人と調剤事務を持っていない人とでは、一緒に入社した時点でけっこう差がついてるとのことです。
(薬剤師の人の話より)
調剤薬局事務をおすすめする人
調剤薬局事務の資格をおすすめする人は、こんな感じです。
- 短期間で資格を取りたい
- 調剤薬局ではたらきたい
- 薬に関わる仕事がしたい
- 処方せんの薬に詳しくなりたい
調剤薬局も、病院と同じく全国各地にあります。
そのため、就職に困らないというメリットが地味にありがたいところ。
「病院で働くのはイヤだけど、調剤薬局ならアリかな…!」
という人におすすめする資格です。
ユーキャンの調剤薬局事務のん届いた❤️❤️
— 。*♡Shion♡*。 (@shionwill0913) January 15, 2021
めっちゃ楽しい〜!!😍😍 pic.twitter.com/Q9PXFKojnr
» ユーキャンで調剤薬局事務を調べる(公式サイト)
※ ① 調剤薬局事務検定試験が受講可能
独学でテキストを買って勉強するのも1つの手です。
調剤薬局事務について詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。
» 【調剤薬局事務】仕事内容・向き不向き・やりがいなど解説!【現場の生の声あり】
【病院を支えたい】看護助手の資格
看護助手は、医師や看護師のフォローをするポジションの仕事です。
受付業務ではなく、患者さんのお世話や看護師さんのフォローが中心です。
看護助手の仕事について
看護助手は、医師・看護師のような国家資格ではないため医療行為を行うことはできません。
しかし、看護チームの一員として
医療機関の中でも大事なポジションに配置されている場合があります。
- 医師・看護師の補助
- 患者さんのお世話
- 院内の環境整備など
- 器具の洗浄、滅菌業務
医療事務の仕事は病院の窓口担当ですが、
看護助手の仕事は病院の医療環境の補助をやるんですね。
そのため体力勝負な仕事が多いですが、パソコン作業が苦手なら看護助手の方がおすすめだったりします。
医療事務、薬局事務はパソコン作業がメインなので、タイピング(文字を打つ作業)や座りっぱなしがイヤなら、看護助手の仕事をおすすめします。
患者さんとうまく会話しつつ、医師や看護師の人と連携して仕事を回していくのが主な仕事です。
看護助手の資格を取る為に勉強中📚📝頑張って資格取って早くこの仕事がしたい😊#看護助手 #ユーキャン #頑張って取得したい pic.twitter.com/FTqAEv6bsv
— ひろみ (@knah_548424) April 17, 2019
看護助手をおすすめする人
看護助手の資格をおすすめするのは、こんな感じの人です。
- パソコン作業が苦手
- 身体を動かした仕事がしたい
- 病院やクリニックではたらきたい
- 自分から動くより、誰かの指示で仕事したい
看護助手は知名度が低いですが、れっきとした医療系資格の1つです。
興味のある仕事だと、資格も高得点も取りやすいのがポイント。
ユーキャンの看護助手資格、終了課題 100点でした✌️✌️最終で100点とれるとは思わなかった。好きなもの(関心があるもの)になると、極端すぎるぐらい出来る。苦手なものと好きなものがあまりにも極端すぎて、自分も驚いている。 https://t.co/rKVFRiltVp pic.twitter.com/0Q2Jav1g08
— きみのぶ 介護福祉士2023受験するよ (@zYlzUhCKDzmKTbL) June 27, 2022
医療事務と看護助手、
どちらも病院で働きますが仕事内容は全然ちがいます。
どっちの仕事をやってみたいか、ゆっくり考えてみてくださいね。
看護助手のテキストは市販で売っていないので、通信講座で資格取得する必要があります。
看護助手の詳しい紹介については、下記の記事をどうぞ。
» 【看護助手】仕事内容・向き不向き・やりがいなど解説!【現場の生の声あり】
【歯医者で働きたい】歯科助手の資格
歯科助手は、歯科医院で就職・仕事するときに役に立つ資格です。
実は私も歯科助手資格を持っていて、過去に歯科医院で仕事をしていたことがあります。
他の資格より知識があるので、わかりやすく解説しますね。
歯科助手の仕事について
歯科助手の仕事は、医院によって受付メインと診察室メインの2種類にわかれます。
- 歯科医院の受付、会計
- レセプト作成(医院による)
- 歯の型取りを作る
- 器具の消毒、滅菌処理
- バキュームの補助
受付メインだと、受付・会計・電話対応が主な仕事です。
診察室メインでは、歯の型取りを作る・器具の消毒をする・バキューム(口の中の水や唾液を吸う機械)の補助をしたりします。
「歯科助手は歯石を取ったり、口の中の掃除をしますか?」と聞かれますが、絶対やりません。
口の中を触ることは医療行為になるため、国家資格である歯科衛生士の資格が必要になるんですね。
もし歯科助手なのに口内清掃の仕事をやっているなら、その歯科医院は法律的にアウトです!
ちなみに、私の勤めていた歯科医院は歯科助手の資格手当がついていました。
(月5000円)
さらに、定期的に歯のメンテナンスをしてもらえたりと、歯科医院ならではの福利厚生があったりします。
歯科助手をおすすめする人
歯科助手の仕事をおすすめする人は、こんな感じです。
- 将来的にずっと使える資格がほしい
- 歯についての知識を勉強したい
- 自分の歯の状況が知りたい
- 歯科医院で仕事をしたい
今日から歯科助手の勉強
— akiha☻ (@exkzh) September 12, 2014
がんばろーー😂💕 pic.twitter.com/pRhsNhUvbX
ちなみに、歯科医院はコンビニよりも数が多いです。
就職に有利で資格手当のあるクリニックも多いので、意外と狙い目の資格ですね。
歯科助手の仕事について、合格後に勉強できる本もあります。
オールカラー印刷で、普段本を読まない人も読みやすいのが特徴です。
歯科助手の資格について、下記の記事で詳しく解説しています。
» 歯科助手資格を詳しく解説
※近日公開予定
【市販薬のプロ】医薬品登録販売者の資格
登録販売者は、市販の薬を販売する仕事です。
お客さんの健康相談や、症状に合った市販薬を選んだりします。
私も持っている資格なので、ちょっと詳しく解説しますね。
登録販売者の仕事について
登録販売者の仕事はこんな感じです。
- 市販薬の販売、陳列
- お薬相談、健康相談
- 市販薬の在庫管理
- レジ打ち、電話対応
- 品出し、清掃 など
市販の薬について、お客さんにおすすめしたり商品のちがいを説明したりします。
また在庫管理や陳列なども行います。
レジ打ちや電話対応など、店舗運営の業務もやったりしますね。
市販の薬についての知識が必要なので、ある程度の勉強が必要になります。
その分、お客さんから直接お礼を言われたり、後日感謝される場合も多いです。
登録販売者をおすすめする人
登録販売者の仕事をおすすめする人は、こんな感じです。
- 将来的にずっと使える資格がほしい
- ドラッグストアで仕事をしたい
- 市販の薬に詳しくなりたい
- 薬が好き
知名度が低くても、直接誰かの役に立つ資格です。
実は、学校に通うこともなく、独学で合格することができたんですね。
医薬品販売業界で仕事したことなかったのですが、、
転職することができ、資格手当によって収入もアップしたのが嬉しいところです。
また、医薬品登録販売者は、免許のようなポジションの資格です。
この資格がないと、ドラッグストアや薬局で市販の薬を売ることができません。
独学でも通信講座でも良いので、取る価値はあります。
ちなみに、私は独学でテキスト1冊で勉強して合格しました。
↑私が使っていたテキスト
登録販売者について、もっと知りたい方は下記の記事をご覧ください。
» 【登録販売者】ぶっちゃける!仕事内容・向き不向き・やりがい【私の経験談あり】
【補足】登録販売者は、他の医療家資格より優遇される
ここまで記事を読んでくれたあなたに、絶対損しない情報をこっそり教えますね。
この記事で紹介した医療系資格のうち4つ(医療事務・調剤薬局事務・看護助手・歯科助手)は、どれも民間資格です。
いわゆる、民間の企業が運営している資格なんですね。
知名度は高いけど、薬剤師や看護師のような国家資格ではありません。
そのため職場によっては「民間資格はあろうがなかろうが評価しない」なんてところもあったりします。
一方、登録販売者資格は「公的資格」に分類されます。
公的資格は都道府県が管轄しているので、その辺にある民間企業が運営する資格と全然ちがいます。
すこし面倒なことに、都道府県の保健所に資格者として登録する必要がありますが、、
保健所に登録するのは、実は薬剤師や看護師と同じだったりします。
資格手当もあるし、エプロン姿の一般従業員とちがい白衣を着て仕事します。
ここで、一般的な民間資格とは明らかに資格の差があるのを知っておいてください。
あなたのライフスタイルに合った勉強方法について
医療系資格について、ここまで読んでくださってありがとうございます。
あなたの気になる資格は見つかりましたか?
取りたい資格が見つかっても、勉強のやり方がわからないと合格は無理です。
そのため、あなたのライフスタイルに合わせた勉強のやり方を教えますね。
【方法1】市販のテキストを使って独学でやる
「独学」は書店、ネット通販で市販のテキスト・教科書を買って、あなた1人で勉強していくスタイルです。
メリット、デメリットはこんな感じです。
- コスト、費用を抑えられる
- 好きな時間に勉強できる
- 途中で挫折しやすい
- やる気がなくなりやすい
- 自分でスケジュールを計画する必要がある
- わからないところを誰かに聞けない
【方法2】通信講座を利用する
ユーキャンのような通信講座を使って、あなた1人で勉強していくスタイルです。
- 自分でテキストを買いにいかなくていい
- どの順番で勉強したらいいかわかる
- 本番のような模擬試験を受けられる
- プロの先生による講義動画を見ることができる
- 費用が少し高い
- 添削問題を提出するのがめんどくさくなる
【方法3】専門学校に通う
高校卒業後や、仕事をやめて専門学校に通うスタイルです。
余談ですが、看護学校だと高卒の人からお母さん世代まで幅広い年齢層がいます。
- 合格までのカリキュラムが充実している
- プロの先生の授業を生で受けられる
- 周りに同じ目標を持つ仲間ができる
- 就職先までバックアップしてくれる学校が多い
- 費用がかなり高い
- 資格取得するまで時間がかかる
このように、それぞれメリット、デメリットがあります。
どの勉強スタイルを選ぶかはあなた次第なので、あなたに合った方法を選んでくださいね。
まとめ:独学で医療系資格は取れる
ここで紹介した資格は、すべて学校に通わなくても取れる資格です。
履歴書の資格欄に書くことで就職・転職に有利になりますし、中には資格手当がつく職場もあります。
あえてデメリットを挙げるなら、どれも国家資格ではないことですね。
※ 医薬品登録販売者は公的資格なので、薬剤師と同じように都道府県への手続き登録が必要です
ここで紹介した医療系資格に少しでも興味があるなら、まずはいろいろ調べてみてください。
クチコミや評判を集めてみて、最終的に受験するか・しないかを決めたら大丈夫ですよ。
【最後に】思い立ったら、すぐ行動しましょう
あなたは「学校に通わなくても取れる医療系資格」を探していたと思います。
もし、ほんの少しでも「気になる資格が見つかった」なら、すぐ行動しましょう。
資料請求するもよし、ノリと勢いで申し込むもよし、テキストを買って勉強するもよしです。
気分が乗ってるのでユーキャン眺めてたんだけど登販も調剤事務も子育て中にオススメの資格って書いてあったそーなんだーと思った
— 蘇生したくましお (@kuma_solt_0201) January 24, 2022
両方取りたいなぁ
ちなみに、資格を取ることが最終目標ではありませんよ。
資格を生かして就職・転職・収入アップが、あなたの最終目標だからです。
ボーナス出るし買ってしまった!登録販売者資格取る!と、決めた!!よろしくユーキャン♪( ´▽`) pic.twitter.com/Lv35ydIn9o
— さらまんだー。 (@lucky_st0616811) December 5, 2018
調剤薬局事務試験合格ε-(´∀`*)ホッ
— リリー・ローズ (@Iq4K8wqoKkuIjiX) April 14, 2022
看護助手は合否まだ。月末頃にはわかるはず!
あとは登録販売者試験前か後に転職したい〜
調剤薬局事務はユーキャンのおかげで一ヶ月で取れた!! pic.twitter.com/ufEjlXJDBK
今日が人生で、1番若い日です。
今から何をするかは、あなた自身で決めてくださいね。
独学でむずかしそうなら、通信講座の検討もどうぞ。
ユーキャン
— かお(iPhone12垢)Wi-Fi環境下のみ (@TIv8CfETp4oGJvR) August 14, 2022
1番欲しい資格
実は
登録販売者 資格
2位 簿記3級
3位 医療事務 か 看護助手
たの性格や、求める職場環境によって選ぶ資格がちがってきます。
医療系資格は、あなたのこれからの人生で強みになりますよ。
気になる資格は、とりあえず資料請求してみるのも1つの手です。
「登録販売者」と「医療事務」のユーキャンの資料、届いたー!
— 愛♡ (@y8_10_19A) January 13, 2018
資格取りたいなって思って応募した✨
あと、調剤薬局事務の資料も頼むつもり🙆⭕頑張ろう😆💪✨ pic.twitter.com/XGlamjUPgP
あなたの気になる資格が見つかったら、ぜひ挑戦してみてください。
ここで紹介した医療系資格については、下記のサイトでくわしく紹介してます。
\ 勉強に自信がない人にオススメ /
あなたの人生の起点になれば、幸いです。
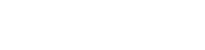






コメント