- 臓器や器官の名前が、なかなか覚えられない
- 第2章の「人体の働きと医薬品」の項目が難しい
- 理科が昔からキライだから、第2章は苦手意識がある
この記事では、登録販売者試験の第2章を攻略するポイントをまとめました。
もし「第2章:人体の働きと医薬品」でつまづいているなら、ご覧ください。
第2章は【人体のしくみ】がテーマ
「第2章:人体の働きと医薬品」では、身体の構造・副作用の種類がおもなテーマになります。
「人体=理系」のような内容ですが、
計算式が出ることはなく、暗記がメインになります。
あなたが学生のときに、理科の授業で習ったことがある知識も試験範囲に入っています。
小中学校の理科の内容をもっと深い内容まで勉強するのが、登録販売者試験(第2章)というわけです。
第2章の試験範囲について
第2章の試験範囲は、こんな感じです。
- 人体の構造と働き
- 胃・腸、肝臓、肺、心臓、腎臓などの内臓器
- 消化器系
- 呼吸器系
- 循環器系
- 泌尿器系
- 目、鼻、耳などの感覚器官
- 目
- 鼻
- 耳
- 皮膚、骨・関節、筋肉などの運動器官
- 外皮系
- 骨格系
- 筋組織
- 脳や神経系の働き
- 中枢神経系
- 末梢神経系
- 胃・腸、肝臓、肺、心臓、腎臓などの内臓器
- 薬が働く仕組み
- 薬の生体内運命
- 薬の体内での働き
- 剤型ごとの違い、適切な使用方法
- 症状からみた主な副作用
- 全身的に現れる副作用
- ショック(アナフィラキシー)、アナフィラキシー様症状
- 重篤な皮膚粘膜障害
- 肝機能障害
- 偽アルドステロン症
- 病気等に対する抵抗力の低下等
- 精神神経系に現れる副作用
- 精神神経障害
- 無菌性髄膜炎
- その他体の局所に現れる副作用
- 消化器系に現れる副作用
- 呼吸器系に現れる副作用
- 循環器系に現れる副作用
- 泌尿器系に現れる副作用感覚器系に現れる副作用
- 皮膚に現れる副作用
- 全身的に現れる副作用
めちゃくちゃ項目多いですよね。
この時点で、勉強する前から苦手意識を持ってしまうんですよ!
(私もそうだった)
ですが、しっかり試験対策をすることで点数を上げることができます。
上記の内容をいかにうまく暗記できるかが、合格への近道になります。
第2章の難易度:そこそこむずかしい
「おい、第2章、難易度高くね?」と思ったあなた。
私も同じ体験をしています。
第1章 → 第2章と順番に勉強していく流れで、やる気が無くなってしまった人も多いんです。
さて、この第2章をどう切り抜けるかが、最初の鬼門となってくるんですよね。
第1章では医薬品の基本的な知識、薬害について勉強します。
第2章では試験範囲がガラッと変わって、人体のはたらきと医薬品という項目です。
胃・小腸・骨・筋肉、神経系など、かつて学生のころに授業で習ったような内容に似ています。
しかし、登録販売者試験では、もっと専門的な内容が出てくるんですよね。
市販薬を販売するうえで、どの成分が人間のどの部分に作用するのかに必要な知識や用語、作用を専門的に覚える必要があります。
第2章の勉強のコツ
登録販売者試験の第2章は、人体の臓器の名称・役割・細胞の種類など、覚えることが多いです。
しかし、そもそもどうやって覚えたらいいかが難しいんですよね。
第2章の勉強のコツは、3つあります。
- 図、イラストを見てイメージする
- YouTube講義動画を活用する
- はたらく細胞のアニメを見る
- 語呂合わせを使って覚える
図、イラストを見てイメージする
登録販売者試験の第2章は、人体の臓器やしくみがメインの範囲です。
専門用語を丸暗記するよりも、
図やイラストを見ることで、よりイメージを膨らませることができます。
中外製薬の「からだとしくみ」というサイトでは、各臓器や気管などのしくみや役割を知ることができます。
※ スマホだとちょっと見にくいのでパソコン推奨
このサイト、私が受験勉強しているときにめちゃくちゃ役に立ちました。
中外製薬の「からだのしくみ」ページ、個人的にかなりオススメ。
— リンネ@多趣味な人、ときどき登録販売者とブログ (@medicamemo) June 17, 2020
・人間の臓器を全て解説
・イラスト盛りだくさん
・わかりやすい言葉使い
・難読単語にルビがある
・神経や免疫なども網羅
人体を勉強するにはうってつけの内容となっている。 私もこのサイトにめちゃくちゃお世話になった。
登録販売者試験で勉強しなくても良い範囲も出てきます。
丸暗記ではなく、イメージをつかみたいときに使うのがおすすめです。
YouTube講義動画を活用する
無料で動画を見ることができるYouTube、
登録販売者試験のための講義動画も投稿されています。
YouTubeで試験によく出てくる重要なポイント・キーワードをチェックできるんです。
YouTubeで「登録販売者」と検索すると、いろんな人の動画が出てきます。
はたらく細胞のアニメを見る
あなたは「はたらく細胞」というアニメを知っていますか?
はたらく細胞とは、人間の細胞がキャラクターとなって、さまざまな仕事をしているところを描いた作品です。
第2章を覚えるときに、いちばん効率的に勉強できる方法だったりします。
休憩中に見てもよし、しっかり勉強したいときに見るのも良しという、登録販売者試験にとってメリットばかりの作品です。
はたらく細胞について気になる方は、下記の記事をどうぞ。
語呂合わせを使って覚える
第2章を効率よく勉強できる方法の1つが、語呂合わせです。
語呂合わせを使うことで、イメージしやすく覚えることができます。
たとえば、こんな感じです。
【神経系の脳について】
脳の血液の循環量 … 約15%
→ 血液は赤い → 赤いのはイチゴ → イチゴ(15%)
脳の酸素の消費量 … 約20%
→ 酸素は化学式だとO2 →O2をひっくりかえして20%
脳のブドウ糖の消費量 … 約25%
→ ブドウ糖は甘い → 甘くてニコニコする → ニコニコ(25%)
この語呂合わせは、石川達也先生がYouTube動画で教えてくれたんですね。
» 登録販売者試験対策合格講座【2章-9】(YouTube)
※ 3:00〜説明してます
私もしっかり覚えられた、ありがたいゴロ合わせです。
語呂合わせが載っている参考書だと、ズル本がおすすめです。
インパクトのあるゴロ、わかりやすい解説が特徴的なテキストです。
語呂合わせをうまく活用することで、時短で効率よく勉強できますよ。
まとめ
第2章は「人体のしくみ」がテーマです。
苦手な人にとっては苦手な分野なので、好き嫌いもわかれます。
あなたのやりやすい方法で勉強を進めてくださいね。
また、第3章も苦手意識の高い人が多いはずです。
どうやって勉強すればいいか悩んでいるなら、下記をご覧ください。
はたらく細胞を使って勉強する方法もどうぞ。
あなたが効率よく勉強できるきっかけになれば、幸いです。
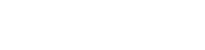



コメント
コメント一覧 (2件)
循環器系、心臓と血液の覚え方のリンクがなくなってるのでしょうか?
リンク先を間違えて設定していたのが原因で、リンクを修正しました。
ぴろーさん、お手数をおかけしました…!